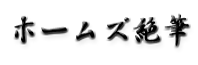|
(2) |
|
|
|
|
ワトスンは彼の書いた回想録のなかでしばしば、ぼくのことを恋愛感情など持たない推理機械だの、女嫌いだのと、女性にはまるで関心がない男のように描いているが、それは事実ではない。
ぼくだって血のかよった生身の人間だし、ひとりの男であることに変わりはないのだ。しかしワトスンがぼくのことをそんな風に思い込むようになった責任の一端はぼく自身にある。というのは、人間の感情、なかでも恋愛感情などというものについては、冷静な理性にもとづく判断力を狂わせるものとして、ぼくはいつもワトスンには嘲笑や皮肉をまじえてしか話したことはなかったし、彼のまとめた回想録のひとつ「四つの署名」では、依頼人として現れた魅力的な女性、メアリ−・モ−スタン嬢をめぐって、ぼくは彼に向かって大見得をきってしまったのだ。メアリ−・モ−スタン嬢ほど聡明で可愛らしく魅力的な女性に出会ったのは、ぼくにとってはそのときが初めてだった。ぼくはワトスンとともに彼女の期待に応えようと事件の解決に全力を尽くした。 |
|
 |
|
聡明で可愛らしく魅力的な女性 |
|
しかし事件が決着したときワトスンはこういったのだ。
「うれしいことにモ−スタンさんが、ぼくとの結婚を承知してくれたんだ」
ああ、そのときぼくはなんという愚かな取り返しのつかない言葉を口走ってしまったの
だろう!ぼくはうめくようにこう言ったのだ。
「そんなことになるんじゃないかと思っていたよ。ぼくは絶対におめでとうとは言えない
ね」それにもうひとつ余計なひと言をつけ加えてしまったのだ。「恋愛というものは感情
的なもので、すべて感情的なものは、ぼくが何物にもまして大切にしている冷静な理性と
は相いれないのだ。判断力が狂うといけないから、ぼくは結婚なんかしないよ」と。
|
どうしてあんなことを言ってしまったのだろう。嫉妬だったのだろうか。いや、それだけではない。ワトスンが結婚すれば、あのベイカ−街の共同生活に終止符が打たれる!そのことがおそらくぼくを圧倒したのだ。ぼくは錯乱していたのだ。感情が理性を支配するという、ぼくのもっとも恐れていた状況に陥ったのだ。
しかし理由はどうあれ、男が一 旦口にした言葉を消すことはできない。相手がいかに親しいワトスンだろうと、男には意地というものがある。それ以後「ぼくは結婚なんかしないよ」と言ったぼく自身の言葉に縛られ、ぼくはワトスンの前で演技しつづけることになってしまったのだ。 |
|
 |
|
モ−スタンさんが、ぼくとの結婚
を承知してくれたんだ |
|
ワトスンがモ−スタン嬢と結婚してべイカ−街を去ったあとは、幸いにも次々と事件が
飛び込んできて、ひとりになったさびしさをかこつひまはなかった。たとえばトレポフ殺
人事件でオデッサへ招かれたり、トリンコマリ−のアトキンソン兄弟の奇怪な事件を解決
したり、あるいはオランダ王室に依頼された事件への対応に忙殺され、ぼくはほとんどの
時間を国外で過ごした。これらの事件を解決してようやくベイカ−街の下宿に戻ったのは
1889年(訳注1)も3月に入ってからのことだった。ぼくがまだ旅装も解かずに、溜
まっていた郵便物を部屋で整理しているときだった。ハドスン夫人が依頼人の来訪を告げ
た。長旅のあとで疲れていたぼくは、とても会う心境ではなかったのだが、よほどのこと
がないかぎりともかく会ってみるのがぼくの営業方針だったので、ぼくはハドスンさんに
来訪者を部屋へ案内するように言った。そして来訪者が部屋に入ってきた瞬間、世界は変
わったのだ。 (つづく)
|
訳注1 ワトスンの記録(「ボヘミアの醜聞」)によれば、1888年のこととなって
いるが、ここではホ−ムズの記述を採用した。
イラスト ストランドマガジン合本1 1891年より(管理人みっちょん) |
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
 |
|