| |
シャーロッキアンの果てしなき冒険 by 水野 雅士
第2章ワトスンのすべて
|

|
2. ホームズとの名コンビ
|
|
ホームズ物語におけるホームズとワトスンの関係は、主従あるいは上下の関係ではありませんが、すでに初対面の場面で見たように、表面的にはホームズがマイペースで走り、ワトスンがこれ追随していくという形に終始し、このパターンは物語の全編を通して変わりません。1903年秋、ホームズが探偵稼業から引退する直前に関わった《這う男》という事件は、公表された60件の事件のうち、事件の発生年月の順ではじつに58番目とされているものですが、この時期においてさえワトスンは「都合よければ、すぐ来い──不都合でも、すぐ来い──S・H」というホームズからの伝言を受け取ると、いやな顔もせずにいそいそとベイカー街へと出かけていくのであります。そのときの様子をワトスンは次のように書きとめています。
ベイカー街へ着いて、わたしが目にしたのは、(略)考えに沈み込んでいるホームズの姿であった。(略)彼は手で、わたしがかつて愛用していた肘掛けいすを指し示したが、これを除けば、それから三十分ものあいだ、わたしが目の前にいることに気づいているような素振りは、少しも見せなかった。やがて、ぴくりと身動きして夢想から目を覚ましたように、いつものあの気まぐれな笑みを浮かべて、かつて慣れ親しんでいたわが家に、よく戻って来てくれた、と歓迎の挨拶をした。「君なら、ぼくが少々夢の中にいたのを許してくれるよね、ワトスン」と彼は言った。
ワトスンが描いたこの寸景からも、ホームズのマイペース振りは明らかであります。にもかかわらず、長年にわたってこの二人の友情が壊れずに続いたのは不思議といえば不思議ですが「シャーロック・ホームズ大事典」の『ワトスンとの相性』の項(執筆 東山あかね)には、心理学者ユングの「男性同士の友情は未熟な無意識的愛であり、深い信頼の世界を作り、自分でコントロールしてぬけ出すことができない」という指摘が取り上げられています。たしかにホームズとワトスンの間に深い信頼関係があったことは間違いのないところですが、それにしても、その友情はワトスンの我慢強い性格と包容力がなければ、とても長続きはしなかったと思われるのであります。ワトスンはホームズに対する自分の立場をきわめて客観的に認識していました。彼はそれをこの《這う男》の別の個所で次のように書き記しています。
|
|
わたし自身も彼の生活習慣のひとつなのだ。だから、わたしは彼のヴァイオリン、シャグタバコ、古びた黒いパイプ、索引帳、それ以外の少々役に立たないものなどを含むたぐいと同列なのだ。事件がおきて、彼が頼れる勇気のある相棒が必要なときは、わたしの役割は明らかだった。けれども、わたしの利用価値はこれだけに留まらなかった。わたしは、彼の精神を研ぎ澄ます砥石であった。わたしは彼に刺激を与えた。彼は好んで、わたしの前で考えを巡らせた。(略) わたしなら表情を表わしたり、合いの手を入れたりするぶんだけ、役に立つというものだ。たとえ、わたしの知性の論理的思考が鈍く、ホームズがいらだつとしても、そのいらだちが、炎のように燃え上がる彼の直観や感受性をいっそう激しく、素早く、引き出させるのに役に立つのだ。
|
|
 |
|
彼のヴァイオリン、シャグタバコ、古びた黒いパイプ、索引帳・・・・
ホームズ博物館にて
撮影 関矢 悦子
撮影日2004年1月4日 |
|
|
|
このなかの「わたしは、彼の精神を研ぎ澄ます砥石であった」とは泣かせる一句であります。このように冷静に自己分析できるところがワトスンのすごいところであります。ワトスンのこの自覚は、決して自虐的なものではなく、頭が切れるという面においては、たしかにホームズほど「clever」ではないかもしれませんが、ホームズよりも「wise」、すなわち賢明で分別があることを示しているとも言えるのではないでしょうか。ホームズ物語の全編を通して、表面的にはホームズがヒーローとして活躍しているように見えますが、実態は「シャーロック・ホームズ大事典」の『ワトスン(の性格)』の項(執筆 東山あかね)に指摘されているように「やはりワトスンのほうがホームズより一回り成熟度が高く、ホームズはワトスンの手のひらの上で躍らされていたような気がする」のであります。
|
|
| それはそれとして、同書の 『ホームズとワトスンとのコンビ』 という項(執筆 笹野文隆)には 「ホームズとワトスンは文学史上最も魅力あるもののひとつであろうが、彼らにはモデルがある。 その最大のものはポーが創ったデュパンと『私』である」とあります。そのほかにも同じくポーの「黄金虫」におけるルグランと「私」、ガボリオの「ルコック探偵」におけるルコックとアブサントの例などが挙げられていて「これらの相棒役はワトスンより単純である」のに対して「ワトスンの役は多彩で、聞き役、記述者、賛美者の他に助手、助言者、護身役、代役、引き立て役等々を兼ね」ていて「ワトスンは一般に考えられているほど単純な人物ではない」ことが指摘されています。また同書には、ホームズとワトスンとのコンビは文学史上のいろいろな二人組が集約された感があるとして、ドイルが参考にしたかどうかは別にして、過去に登場した多くの二人組が、ホームズ対ワトスンの原型として紹介されていて、まことに興味深いものがあります。 |
|
 |
|
街を散歩するホームズとワトスン
(シドニー・パジェット画)
《入院患者》より
|
|
ところで《入院患者》という作品が「ストランド・マガジン」に掲載された際のシドニー・パジェットのさし絵に、ホームズとワトスンが親しげに腕を組んで街を歩いているシーンがありますが、ヴィクトリア朝時代には親しい間柄の男同士が腕を組んで歩くのが普通であったという事情──たとえば右側のさし絵にも見られるとおり──を知らないと、現代の感覚で見るかぎり「ホームズとワトスンの関係はゲイだったのか?」というような、あらぬ憶測を生み出しかねません。この問題については「シャーロック・ホームズ 事件と心理の謎」(ジョン・ラドフォード著 小林司・東山あかね・熊谷彰訳 講談社 2001年刊)において、さまざまな角度から心理学的に検討が加えられ、結論が出されています。
ホームズとワトスンがホモの関係にあったかどうかというようなことは考えたくもない真面目で純粋なファンの方々はご安心めされたし!
|
 |
|
We passed down boulevards.
ストランド・マガジン1891年10月号掲載
Jacques Normand著
The P.L.M.Express.より
|
|
|
|
結論だけ述べるならば、答は「ノー」であります。つまり、ホモではなかったと診断されているのであります。また、ホームズとワトスンのあまりの親密さに、名探偵ネロ・ウルフを生んだレックス・スタウトが「ワトスンは女であった」という奇説を唱えたのに対して、シャーロッキアンのジュリアン・ウルフは「ワトスンは女ではなかった」と反論しています。これらの論文の邦訳は、すでに絶版ではありますが「シャーロック・ホウムズ読本」(エドガー・W・スミス編 鈴木幸夫訳 研究社 1973年刊)に収録されています。また、わが国のシャーロッキアン中川裕朗は「ホームズは女だった」(中川裕朗著 早川書房 1980年刊)という、これまた奇想天外な説を唱えていることを付け加えておきましょう。
|
|
| 「シャーロック・ホームズ 事件と心理の謎」(ジョン・ラドフォード著 小林司・東山あかね・熊谷彰訳 講談社 2001年刊) |
|
「シャーロック・ホウムズ読本」
(エドガー・W・スミス編 鈴木幸夫訳 研究社 1973年刊)
|
|
「ホームズは女だった」
(中川裕朗著 早川書房 1980年刊)
|
 |
|
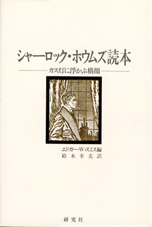 |
|
 |
|