| ただいまご紹介に与りました水野でございます。本日はようこそ「シャーロック・ホームズの世界」の講座へお越しくださいました。こういった分野もまた生涯学習の一つの対象となり得るのだということをみなさまにお伝えする機会を得ましたことをたいへんうれしく思っております。本日は二時間という限られた時間ではございますが、この豊穣で知的な世界のほんの一端をご紹介させていただきたいと存じますので、定年退職後の自由な時間をこんな風に使っているヤツもおるのか、というくらいの感じで、気楽に聞き流していただければ幸いでございます。 |
| これはシャーロック・ホームズの肖像画であります。聡明さを思わせる広い額、意志の強そうな顎の線、神経質そうな表情など、ホームズの特徴がよく出ている絵ですが、これを描いたのはシドニー・パジェットという挿絵画家であります。十九世紀末に英国の「ストランド・マガジン」という月刊雑誌に「シャーロック・ホームズ物語」の短編の連載が始まりますと、これが爆発的な人気をさらったのでありますが、パジェットはそのとき挿絵を担当していた人であります。この人は挿絵画家のなかでは、最もたくさんホームズ物語の挿絵を描いた人で、彼は47年という短い生涯にホームズ物語の挿絵を356枚描きましたが、彼の重厚な画風がホームズのイメージを読者に定着させてしまってと言っても過言ではありません。それはほとんど決定的といえるものでした。と申しますのは、そのあと多くの挿絵画家がホームズを描きましたが、すべてパジェットの影響を受けざるを得なかったのであります。つまり、パジェットと違ったイメージのホームズを描くと、ホームズらしくないということで読者に受けなかったのであります。 |
|
 シャーロック・ホームズ シャーロック・ホームズ
|
|
ところでこの絵は、じつはホームズ物語の何処を探しても見つからないのであります。なぜかというと、これは挿絵として陽の目を見たものではないからであります。パジェットはこの絵を描いたあと、気に入らなくてゴミ箱に捨てたのを、あとで奥さんが拾い出して取っておいたものといわれています。いわばパジェットの357枚目のホームズの挿絵といってよいものでありまして、彼の死後44年も経った1952年に英国の「コーンヒル・マガジン」という雑誌に掲載されて一躍有名になったものであります。皮肉なことに現在ではこの肖像画はパジェットが描いたホームズのなかでも、もっとも出来のよいものの一つとしてもてはやされているのであります。
シャーロック・ホームズが初めてこの世に登場しましたのは、1887年に発表されました《緋色の研究》という長編の作品であります。1887年といいますと、わが国では明治20年にあたります。この年、東京電力の前身であります東京電灯が送電を開始して、かの有名な鹿鳴館にも初めて白熱電灯がともったという記録がありますので、その古さ加減がおわかりいただけるかと思います。今年は2008年ですから、ホームズが《緋色の研究》で初めてこの世に登場した1887年から数えてちょうど121年目になるわけであります。 |
ホームズ物語の作者は、ご承知のとおり、英国のアーサー・コナン・ドイルという、医者から転向した作家であります。この写真はちょうど《緋色の研究》を執筆していたころのものといわれております。彼は1859年にスコットランドのエディンバラでカトリック教徒の家庭の長男として生まれまして、エディンバラ大学の医学部を卒業したあと英国南部にある軍港として有名なポーツマスの近郊のサウスシーというところで医院を開業しましたが、さっぱり流行りませんでした。そこで彼は生れつき、ものを書くことが好きで、学生時代から雑誌に作品を投稿して採用されたりしていましたし、すでに結婚もしていましたので、生活費の足しにしようとして、医院で患者がくるのを待っている間に書き上げたのが《緋色の研究》だったのであります。つまり医院のほうは、患者を待つ間に小説が書けるくらいヒマだったのであります。
ドイルはすでに探偵小説の父といわれる米国のエドガー・アラン・ポーや、フランス探偵小説の父と呼ばれることもあるエミール・ガボリオといった先輩たちの探偵小説を愛読していまして、いつかは自分も探偵小説を書いてみたいと常々考えていたのであります。そこで彼はエディンバラ大学の医学部の恩師であるジョジフ・ベル博士をモデルにすることを思いついたのであります。 |
|
|
 |
|
コナン・ドイル
|
|
ドイルは晩年に書いた自伝のなかで「私は医学部の恩師ジョゼフ・ベル博士のことを思い出し、もしあの人が探偵だったらこの探偵という仕事を精密科学の領域にまで引き上げただろうと考えた」と述べています。またドイルは同じ自伝のなかで、ベル博士に関するエピソードをいくつか紹介していますが、その一つに、たとえば次のようなものがあります。あるときベル博士は、臨床講義、つまり実際に患者を診察し治療するところを生徒に見せる講義のことですが、その臨床講義で、診察室に入ってきた患者をじっと観察してこう言いました。
「君は軍隊勤務をしたな」
「はい」と患者が答えます。
「除隊後間もないね」
「そのとおりです」
「スコットランド連隊だね」
「はい、そうです」
「西インドのバルバドス諸島に駐屯していたね」
「おっしゃるとおりです」と患者はおそれいって答えました。 |
|
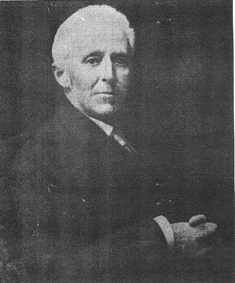
ジョゼフ・ベル博士
|
|
そこでベル博士は生徒たちのほうを向いて次のように説明したのであります。
「さて諸君、この患者は見るからに教養のありそうな感じの人だったが、部屋へ入ってきて帽子をとらなかった。軍隊では帽子を取る習慣がないからだ。しかし除隊してから長く経っていたら普通の市民の作法どおり帽子を取っていただろう。彼の言葉にはスコットランド訛りがあり、態度には威厳があるので、明らかにスコットランド人だ。だとすればスコットランド連隊に配属されるのが普通だ。この患者の症状は象皮病であり、これは西インド諸島に特有の風土病で、わが国でかかる病気ではない。英軍の西インド諸島における駐屯地はバルバドス諸島なのだよ」万事こういう調子だったので、生徒たちは大いに感銘を受けたとドイルは自伝に書いています。つまりベル博士は学生たちに、患者を診断するには、目で見るだけではなく、観察せよ。そして頭を使え。持てる知識を総動員せよ、ということを身をもって学生たちに教えたのであります。 |
|
|