ところで、せっかくドイルが書き上げた《緋色の研究》の原稿は出版社をたらい回しにされたのち、ワード・ロック社という出版社がやっと拾ってくれまして、約一年半の後に「ビートンのクリスマス・アニュアル」という雑誌に掲載されたのであります。これがその「ビートンのクリスマス・アニュアル」であります。表紙のケバケバしさを見ただけでも安っぽい三文雑誌であることがお分かりいただけると思いますが、いまではこれが世界で数冊しか存在が確認されていない超稀覯本でありまして、シャーロッキアンのなかでも、特に初版本のコレクターにとっては垂涎の的なのであります。たまたま今年の五月に英国のオックスフォードで開かれたオークションに一冊これが現われまして、なんと18600ポンド(約380万円)で落札されたと聞いております。まあ、マニアとなると、ここまでやる人もいるのであります。
しかし「ビートンのクリスマス・アニュアル」に発表された当時、この《緋色の研究》については、新聞雑誌に若干の好意的な書評は出たものの、世間から特段の注目を集めることはありませんでした。いまでは世界中知らない人はいないシャーロック・ホームズですが、そのデビューはこのように寂しいものだったのであります。この《緋色の研究》は、読んでご覧になると、おわかりになりますが「ぼくだって探偵小説くらい書ける」というドイルの自負と気負いみたいなものが感じられる、新鮮でなかなかよくできた作品であります。少なくとも私はそう感じています。長編とはいいましても、文庫本にして200ページほどの薄っぺらなものですし、ホームズを語るときには、欠かせない作品の一つでありますから、もしまだ読んでおられなければ、是非一読をお薦めいたします。私のもっているのは一つは昭和58年版の新潮長文庫で定価220円でしたが、最近買った光文社文庫版の一番新しいホームズ・シリーズでは、税込みで500円になっていました。
これはホームズ物語の第二作《四つの署名》が発表された米国の雑誌「リピコッツ・マガジン」の1890年2月号であります。《緋色の研究》が発表された翌年の1888年に、意外にも「リピンコッツ・マガジン」という米国の雑誌社から、ドイルに執筆依頼がきたのであります。第一作の《緋色の研究》は、英国本国ではあまり評判になりませんでしたが、当時はまだ米国に著作権の設定がなされていなかったので、米国では英国の本を無断で出版することができたのであります。《緋色の研究》には、北米大陸のユタ州ソルトレークシティのモルモン教の世界を舞台にした劇中劇が挿入されていますが、そのせいか米国で出版された《緋色の研究》はかなりの評判をとっていたのであります。
|
|
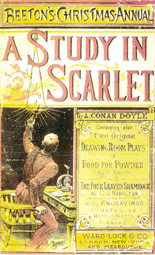
ビートンのクリスマス・アニュアル
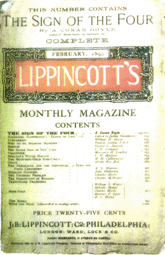
リピコッツ・マガジン
|
そこで米国のリピンコッツ社は、当時ヨーロッパを蔽っていたデカダンス、つまり耽美主義とも退廃主義とも呼ばれた運動の先頭に立っていたオスカー・ワイルドと、お堅いほうを代表するコナン・ドイルとを競い合わせる企画を立てたのであります。
オスカー・ワイルドはこのとき、「ドリアン・グレイの肖像」を書きましたが、これはいまでは彼の代表作の一つとして評価されているものであります。このときドイルのほうは《四つの署名》というホームズものの長編第二作を書いたのですが、これも大した話題になることはなく、世間から忘れ去られていったのであります。
|
|

オスカー・ワイルド
|
| 第二作の《四つの署名》が発表された翌年の1891年1月に「ストランド・マガジン」というインテリ向け月刊誌が創刊されました。これはわが国の「文芸春秋」クラスにイラストを多くしたような雑誌でありまして、産業革命で急増した中産階級の知的需要を当て込んで創刊された雑誌であります。この年の7月号からこの雑誌にホームズものの短編を連載することとなったのですが、連載が始まるやいなや、これが大変な人気となりまして、雑誌の発行部数も三十万部から一挙に五十万部へと跳ね上がったといわれています。そしてドイルはまたたく間に流行作家として不動の地位を獲得したのであります。それ以後1927年まで、すなわち《緋色の研究》が初めて世に出た1887年から数えますと、じつに四十年にわたり、熱狂的な読者の要望と、出版社からの度重なる要請に尻を叩かれながら、長編四編、短編五十六編の合計六十編におよぶホームズ物語を書き続けることになったのであります。これがその、ホームズ物語の短編の連載が始まった記念すべき「ストランド・マガジン」の1891年7月号であります。 |
|

ストランド・マガジン」の1891年7月号 |
| ドイルはやがて国内ばかりか、外国にも広く名前を知られる有名人となりました。ちなみにわが国には1890年(明治23年)ごろには、すでにドイルの名が紹介されており、1894年、つまり明治27年の1月には「日本人」という大衆雑誌に《乞食道楽》という表題の作品が翻訳されて掲載されています。これは「ストランド・マガジン」に掲載された原作の《唇のねじれた男》(The Man with Twisted Lips)の挿絵の一つであります。昔から「乞食は三日やったらやめられない」と言いますが、これは乞食をやめられなくなる男の話でありまして、本国で発表されたのが「ストランド・マガジン」の1891年12月号ですから、それから遅れることわずかに2年1ヶ月の1894年1月には日本で《乞食道楽》として翻訳が発表されていますから、当時としてはかなり早いタイミングでわが国に入ってきたことがわかるのであります。 |
|

乞食姿のネヴル・セントクレア |
これは1921年にコナン・ドイルが家族をつれて米国へ講演旅行したときのスナップ写真ですが、ここに写っているドイルの末娘のジーンさんは、晩年になって思い出話として、ホームズに関する話をすることは父の機嫌が悪くなるので、家庭のなかではタブーだったと語っています。つまりドイルはシャーロック・ホームズのお蔭で冨を手に入れ、作家として押しも押されもせぬ地位と名声を確立したのですが、それにもかかわらず、シャーロック・ホームズの作者と呼ばれることを好まなかったようであります。
ドイルは子どものときから猛烈な読書家で、日に三回も本を取替えにきてはいけないと図書館の窓口で注意されたことがある、と自伝に書いていますし、かつ彼は博覧強記で、読んだ文章をきわめて正確に覚えていたといわれています。そういった生まれながらの才能を持ったドイルは、子どものころから有名な歴史家マコ−レーに傾倒するようになりまして、歴史小説家こそ自分の本領であると考えていたのであります。実際、彼は《四つの署名》を発表した同じ年にロングマンズ社というところから「マイカ・クラーク」という歴史小説を発表しておりまして、それがそこそこの評価を得ていましたので、生活のためにアルバイトで書き始めたホームズものがヒットしたからといって、彼自身が一段低く見ていた通俗小説の作家として世間に名前が通るのは、沽券にかかわると思っていた節がみられるのであります。ここに彼のプライドというか、ドイルという人物の一側面を垣間見ることができるように思われます。 |
|

ドイル一家の写真と娘のジーンさんの晩年の写真 |
|