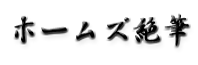|
(15)
|
|
|
|
|
ぼくの計画は思ったとおりに運んだ。アイリ−ン・アドラ−がゴドフリ−・ノ−トンという男を愛し、その男と結婚式を挙げたことにしたのも、ぼくの追求の手を逃れて彼女が新婚の夫と共にイギリスを脱出したことにしたのも、すべてぼくが作った筋書きだった。とくにアイリ−ンの置き手紙の効果は絶大だった。ぼくは事前の打合せで、彼女に置き手紙のアイデアを示唆し、その目的と主旨について簡単に説明しただけだったにもかかわらず、それを完全に理解し、あれほどまで具体的かつリアルに書き上げた彼女の文才はまさに感嘆すべきものであった。その結果陛下は写真の奪回を諦め、計画は成功したのだ。
「敵を欺くにはまず味方を欺け」という。ワトスンには申し訳なかったのだが、将来再び陛下の心をかすめるかもしれないアイリ−ンからの脅迫という不安を完全に払拭し、ひいては陛下の手のものの監視の目からアイリ−ンを永久に解放するためには、ぼくの描いた筋書きが事実であると陛下に信じてもらうことが是非とも必要だった。 |
|
| そのためには、しらっぱくれる才能ときたらからっきし駄目だが、事件の経緯を証人の目で忠実に記録し生き生きと表現することにかけては素晴らしい才能を持つワトスンに、まずぼくの描いた筋書きをすべて真実と思い込んでもらわなければならなかったのだ。陛下が初めてぼくを訪ねてきたとき、ワトスンがそばにいたのは偶然だったが、ぼくがひとつのアイデアを思いついたという意味では、それはきわめて幸運だった。ぼくはそのアイデアに基づいてワトスンに火事騒ぎを起こす役割を演じてもらったので、彼はまさに事件の渦中の人になった。それに、女性の本能的な衝動を利用したぼくの計略が、アイリ−ンの機知の前に無残にも破れ去るという設定は、ワトスンにとってきわめて印象的だったはずだ。 |
すでに「緋色の研究」や「四つの署名」と題する回想録を発表していたワトスンならば、必ずや近い将来この事件も回想録の題材に取り上げて、公表してくれるとぼくは考えたのだ。
案の定ワトスンは、秘密を守ると陛下に約束した二年を過ぎると「ボヘミアの醜聞」と題してこの事件を公表した。もちろんボヘミア国王も、その婚約相手であるスカンジナヴィア国王の王女クロチルドもすべて仮名(かめい)であって、依頼人の秘密を守る配慮がなされていた。だからぼくも最初から、ワトスンが用いた仮名をそのまま使ってこの手紙を書いているのだ。しかもワトスンは、ぼくが期待したとおり、この事件を非常に魅力的な物語に仕上げたので、ぼくの関わった事件記録が「ストランド・マガジン」に短編シリ−ズで連載されることが決まったとき、彼はこの物語を最初に持ってきたほどだった。 |
|
「ボヘミアの醜聞」がもしも陛下の眼にとまっていたならば、事件の当事者である陛下の眼には、名前が変えてあることを除けば、すべてが事実の忠実な記録として映ったにちがいない。将来、陛下の胸に「もしや再びアイリ−ンから脅迫されることになったら?」という不安が去来することがあるとしても、物語のなかに忠実に再現された置き手紙の内容や、それを陛下とぼくとワトスンの三人で実際にのぞき込んだあのときの状況を思い出せば、陛下の懸念は「そんなことはあるはずがない」という安堵へと切り替わるであろう。
ああ、しかし、何ということだ! ぼくは決定的な過ちを犯したのだ。せっかくここまで計画どおり運んだというのに!「ボヘミアの醜聞」が陛下の眼にとまる必要さえなくなってしまったのだ。神はなぜぼくにこのような厳しい試練をお与えになったのだろう?
思い出すだけで、なんだか疲れがどっと出てきた。今日はここで筆を擱くことにする。つらい話だが、詳しくは次の手紙以降で話すことにしよう。それがぼくのこの懺悔の核心なのだ。神よ、いましばらくの間,私に命をお与えください。では、ご機嫌よう!
きみの
シャ−ロック・ホ−ムズ |
|
|
(つづく) |
| |
イラスト ストランドマガジン合本2 1891年「ボヘミアの醜聞」のイラストです
ストランドマガジン合本1の表紙です
管理人みっちょん
|
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|