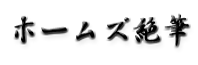|
(16)
|
|
|
|
|
おはよう。今日は体調がいいので、どんどん書けそうだ。
火事騒ぎを起こしたあと、ぼくはアイリ−ンを取り敢えずロンドン市内にあるぼくの隠れ家のひとつにかくまった。そこはモンタギュ−・プレイスの一角にあり、ぼくが持っている隠れ家のなかでは狭いながらもいちばん小綺麗で、周囲の環境も隠れ家として最適だった。あの晩、ベイカ−街に帰り着いたぼくに「こんばんは、シャーロック・ホームズさん」と彼女が挨拶したのは、あらかじめ打ち合わせてあった「準備完了」の合図だったのだ。つまり「引っ越しの手配も、置き手紙の準備も、すべて完了しました。ブライオニ−荘へはいつ来られても大丈夫です。私は用意していただいた隠れ家へこれから参ります」ということを意味していたのだ。
次の日、ぼくは街の浮浪児で組織した「ベイカ−街不正規連隊」のリ−ダ−であるウィギンズを呼び、隠れ家の周辺を交替で常時見張るよう命じ、何か変わったことがあればすぐに知らせるように言いつけた。 |
|
もちろん、ぼく自身もそれ以後は日を置かず彼女を訪ねた。尾行されないように十分注意し、ときには変装までして、きわめて慎重に行動しなければならなかったが、彼女の不便になった日常生活を助けるために彼女の手足となることは、何にもまさるぼくの喜びであり、ぼくの生き甲斐だった。とはいえ、オペラ歌手として世間に知られている彼女を、いつまでもその状態にしておくわけにはいかなかった。彼女がロンドンにいることをボヘミア王家に知られてはまずかった。ぼくは前述したフランスの探偵、フランソワ・ル・ヴィラ−ルに連絡をとって事情を説明し、パリに住処を見つけてもらい、彼女を送り出すことにした。そして彼に彼女の警護を頼んだ。別れはつらかったが、これもぼく自身が描いた筋書きであり、曲げるわけにはいかなかったのだ。
いよいよチャリング・クロス駅から大陸へ旅立つ彼女を見送る日がきた。その日ぼくはノ−サンバ−ランド・アヴェニュ−の横丁を入ったところにある、目立たない小さな料理店で彼女と夕食をともにした。彼女は相変わらず美しかった。旅慣れている彼女は、ほとんど黒に近い濃紺のシンプルな旅行用ス−ツに同色系のつば広の帽子、それに白のハンドバッグという出で立ちで、大型のス−ツ・ケ−スをひとつポ−タ−に運ばせているだけだった。夕食にはまだ少し早い時間だったせいか、店は空いていて静かだった。彼女は席につくと改まって言った。 |
「ホ−ムズさまには、何から何までお世話になりまして、お礼の言葉もございません。ほんとうに有り難うございました」「とんでもありません。でも事件はまだ完全に解決したわけではありません。いくつか残っている疑問点を解明するまで、まだまだ油断はできません。気をつけてくださいよ、ミセス・ノ−トン」冗談めかしてぼくが言うと彼女は笑った。「困ったことがあったら、いつでもご一報ください。飛んでいきますから。ル・ヴィラ−ル君にもよく頼んでありますから、緊急の場合は彼に相談されるとよいでしょう。ではお元気で!」二人は乾杯した。
ぼくにとって至福の時間はまたたく間に過ぎ去った。デザ−トも終わり、そろそろ出発の時間が気になり出したところで、ぼくはようやく食事中ずっとどう言おうかとあれこれ考えていたことを切り出した。ぼくは思い切って彼女に結婚を申し込んだのだ。 |
|
| いまにして思うと月並みな文句だが、そのときのぼくは無我夢中だった。ぼくは、もしもこのプロポ−ズを受けてもらえるとしたら、彼女を幸せにするためにぼくができることはどんなことでもするつもりでいること、ただし、当時ぼくは探偵として生涯を賭けた大仕事に取り組んでいたので、結婚はそれを片づけてからにしたいこと、そのあとは、彼女が望むなら探偵業を引退してもよいと思っていること、彼女の仕事は結婚後もこれまでどおり続けてもらって一向にかまわないこと、返事は大陸に着いてからでもよいから考えておいてほしいことなど、想いのたけをひと息に話した。ぼくはシャ−ロック・ホ−ムズの衣を脱ぎ捨て、ひとりの男として愛を告白したのだ。 |
|
|
(つづく) |
| |
イラスト ストランドマガジン合本9 1895年に載っているイラストを合成したものです
ストランドマガジン合本27 1904年「一人きりの自転車乗り」の画像を合成したものです
管理人みっちょん
|
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|