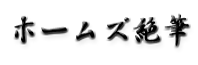|
(21)
|
|
|
|
|
モリア−ティ教授がようやく口を開いた。
「きみは思ったほど前頭葉が発達しておらんようだね。ガウンのポケットのなかで、弾丸の入ったピストルをもてあそぶようなことをするのは、じつに物騒な習慣だ。どうやら私という人間をご存知ないようだな」
ぼくは、撃鉄を起こしたままピストルをテ−ブルの上に置いた。
「どういたしまして。きみのことはよく知っているつもりだ。ぼくが知らないだろうときみが思っている多くのことを、実はぼくが知っているのだ」
「たとえば、どんなことを?」
「たとえば、きみがボヘミア国王を脅迫していたことも、アイリーンを死にいたらしめたのがきみだということも、ぼくは承知している」「ほう。さすがホ−ムズ君だ。きみがどうしてそれを知ったのか、少しばかり興味があるね。話してはくれないかね」 |
|
「簡単なことさ。ワルシャワの写真館の主人が死亡した状況を聞けば、これが名人の筆さばきであることがわかる。つまりきみの作品であることは明らかだ。ぼくの目はごまかせないよ。アイリーン自身は空き巣や強盗に少なくとも八回は狙われたといっていたのに、ボヘミア国王が彼女の身辺を洗ったのは五回だといっていた。ということは、国王以外の何者かが写真を探していることを物語っている。つまり国王が雇った盗賊のなかにきみの手下が紛れ込んでいたので、きみがあの写真の存在を知ったというわけだ。
ところがきみの手下はぼんくらばかりだから、アイリ−ンの隠した写真をなかなか見つけ出せない。業を煮やしたきみはボヘミア国王を動かして、ぼくに写真を捜させようとした。きみはたまたま国王の婚約発表が迫っていたことを利用して、例の写真を相手方に送るぞと脅迫のにせ手紙を国王に送りつけたのだ。国王はアイリーンに脅迫されたものと思い、あわててぼくのところへ相談にきた。ここまではきみの思惑どおり運んだが、ぼくは国王に写真の奪回を諦めさせてしまったし、アイリ−ンはどこかへ行方をくらましてしまった。きみとしてはあてが外れたというわけだ 」「ご明察のとおりだよ、ホ−ムズ君。敵ながらあっぱれだ。破滅させるには惜しいね」 |
「言っとくが、破滅するのはそっちだよ」とぼくは切り返した。「しかし、きみはなぜワルシャワの写真館の主人まで殺さねばならなかったのかね?」 「そりゃあ、あの男が、乾板が紛失しただの、盗まれただの、なんだかんだ言ってネガを渡そうとしなかったからだ」
「しかし、盗まれたのは事実だったのだ。ボヘミア国王が先手を打って処分したのだ」「ふむ。そうかもしれぬ。しかし、そんなことは問題ではない。一匹狼のきみにはわからぬかもしれんが、組織を維持するためには,私の命令には絶対服従するという鉄の規律が必要なのだ。それは組織の外にいる者に対しても組織の内部に対するのとまったく同じように適用しなければならない。組織のメンバーに対するみせしめのためだよ。理由がどうあれ例外はない。私の命令に従わない者に共通の運命は死なのだよ、ホームズ君」
「アイリ−ン・ノ−トンの死も、地元警察ではスキ−の事故死として処理されてしまったが、きみの仕わざであることははっきりしている。ぼくにはそれが手にとるようにわかるのだ。 |
|
あれは事故死ではあり得ないのだ。なぜなら、もっとも基本的なところに矛盾があるからだ。プロの俳優や歌手というものは──ぼくも若いころ演劇のまねごとをやったことがあるからわかるんだが──公演期間中は舞台に穴をあけることがないよう、日常生活に十分な注意を払い、自己管理に努めるものなのだ。たとえ自分がどんなに得意なスポ−ツであったにせよ、ちょっとしたはずみで骨折などの危険性をともなうスキ−を、彼女が公演期間中にやることは絶対にあり得ないのだ。覚えておくんだ、モリアーティ教授。ぼくはきみを決して許しはしない。たった一枚の写真を渡さないからといって、なぜきみは彼女を ・・・ 」
ぼくは再びこみ上げてくる怒りに言葉を失った。
「おやおや、これは驚いたね、ホームズ君。きみは彼女に惚れたのか? たった一枚の写真と言うが、きみにはあの写真の価値がわからないのかね? 使い方によっては、ボヘミア国の領地の一部を割譲させるほどの値打ちがあったことぐらい、きみも先刻承知のはずじゃなかったのかね? いまではボヘミア王家とスカンヂナヴィア王家とは結ばれてしまったが、それでもまだボヘミア王家のスキャンダルとして使えないことはない。いや、以前にまして利用価値が高まったともいえる。それともきみは彼女に首ったけで、目が見えなくなったのかね? あの写真は、彼女が隠し持っていようと、きみが預かっていようとどちらでもよかった。彼女が大陸にいることがわかった以上、彼女が『写真をわたせ』という私の命令におとなしく従うかどうかが問題だったのだ。ところが彼女は私の命令を無視した。私に逆らったのだ。彼女はみずから死を選んだも同然なのだ」
冷然と言い放つモリア−ティ教授の言葉は、ぼくに彼の息の根をとめる決心をさせるに十分だった。しかし、その場で行動を起こすわけにはいかなかった。彼の組織全体を粉砕しなければならないのだ。そのためには数カ月にわたり苦心して張りめぐらした包囲網が完成するまで、もう三日待たなければならなかった。そうすれば、一九世紀最大の一斉検挙が行われ、それに続く刑事裁判が四十件以上の迷宮入り事件を一挙に解決し、捕らえられた一味全員が絞首刑になるはずだった。早まったことはできなかった。しかし、正直なところ、ぼくはモリア−ティだけは法律の手によって裁くのではなく、自分のこの手で裁きたいという気持ちを抑えきれなかった。 |
|
|
(つづく) |
ストランドマガジン 合本6号1893年に載っていたものです
ホームズ絶筆(5)に使用した画像です
管理人みっちょん
|
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|