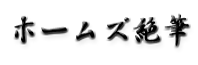|
(23)
|
|
| 翌日ぼくたちは、山越えした先のロ−ゼンラウイで一泊するつもりで「英国旅館」を出発した。ワトスンには言わなかったが、前の晩、旅館の周りをうろうろする背の高い猫背の姿を見かけたので、ぐずぐずしてはいられなかった。ただ、旅館の主人ペ−タ−・シュタイラ−の強い勧めに従い、途中少し回り道をして、半マイルほど登ったところにあるライヘンバッハの滝を見に行った。それは恐ろしいところだった。雪解けで増水した巨大な奔流が奈落の底に向かって凄まじい勢いで落下し、耳をろうする轟音をあげていた。そこへスイス人の少年が手紙を持って走ってきた。手紙はさっき出発してきたばかりの「英国旅館」の主人シュタイラ−からのものだった。手紙の内容は「旅館に投宿したイギリスの婦人が喀血したので、戻ってきてもらえれば有り難い。イギリス人の医者に診てもらえれば、大変なぐさめになると思う」というものだった。 |
|
| そこでワトスンは、夜ロ−ゼンラウイでぼくと落ち合う約束をして旅館に戻って行った。ぼくはそのあとで、使いの少年も帰した。その少年は実はぼくが昨夜のうちに雇っておいたもので、これから起こる危険からワトスンを遠ざけるために、わざとにせ手紙を届けさせたのだ。 |
| ぼくは一人っきりになると、急いで岩場を伝って見晴らしのよい高みへのぼった。そこからは、滝まで登ってくる小道が山肌に沿ってくねくねと見え隠れしながら続いているのが見下ろせた。思ったとおりその道を一人の背の高い人影が急ぎ足で登ってくるのが見えた。だんだん近づいてくるにつれて、右手に何か握りしめているのがわかった。用意してきた双眼鏡で見ると、それはピストルだった。ぼくは急いで小道まで下りてきて、滝壺の断崖にいちばん近い岩陰に身を隠した。人影が近づいてきて、ぼくの目の前を通り過ぎようとした瞬間、ぼくは躍り出てその人影の右手をアルペンストック(登山杖)で打ち据えた。ピストルはごつごつした岩場に、音をたてて落ちた。ぼくはすかさずそれを激流うずまく谷底へ蹴落とした。一瞬の出来事に相手は棒立ちになった。 |
|
「待っていたよ、モリア−ティ教授。きっとくると思っていた。マイリンゲンへきて、この滝を見ないで帰る人なんていないからね。ライヘンバッハの滝へようこそ!」
ぼくは上機嫌で言った。相手は憤怒の形相もすさまじく、左手に持っていたアルペンストックを右手に持ち替えて殴りかかってきた。日ごろ頭脳だけを使って生きてきた哀れな敵は、フェンシングの基本すら習得したことがないらしく、やたらに杖を振り回すだけだった。子どものころから大学時代までフェンシングの腕を鍛えてきたぼくにとっては、これをかわすことくらい赤子の手をねじるようなものだった。ぼくは自分の杖で二、三丁相手の攻撃を受け止めたあと、簡単に相手の杖を叩き落した。生涯にただ一人、ぼくがもっとも真剣に、もっとも深く愛した女性アイリーンを葬り去った男に償いをさせるときがついにきたのだ。
ぼくはこのタイプの男は、プライドを傷つけられることが──ぼく自身もそうなのだが──もっともダメ−ジが大きいことを知っていた。彼は態勢を立て直し、今度はナイフを手にして再び身構えたが、ぼくは平然として言葉で相手を鞭打った。アイリーンの無念を思うと、ぼくも決して冷静でいたわけではないが、こちらが冷静を装えば装うほど、相手は熱くなり、逆上するのだ。
「きみにはここで死んでもらうんだから、そうあわてなさんな。ぼくは自分の手できみを殺害することに決めたんだ。それには、法秩序の厳しい英国内ではちょっと面倒だ。だからここまで足をのばしたのだ。きみの手下はみんな捕まってしまったから、きみがぼくを恨むのも無理はない。きみは必ず復讐の鬼となって、ぼくを追っかけるだろうと思っていたよ。きみにとってはスコットランド・ヤ−ドの連中の包囲網をくぐりぬけてくるくらいは朝飯前だろうからね。きみはぼくの期待に応えてここまできてくれたというわけだ」
「うお−っ」相手は額に青筋を立て、わけのわからない叫び声をあげ、再び飛びかかってきたが、逆上すれば手元も狂いやすい。ぼくはこれも難なくかわした。 |
|
|
(つづく) |
ストランドマガジン 合本6号1893年に載っていたものです
ストランドマガジン 合本1897年に載っていた画像と上記の画像を合成したものです。
管理人みっちょん
|
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
 |
|