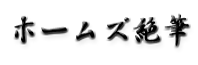|
(最終回)
|
|
| 「ぼくはきみが追いかけやすいよう配慮したつもりだ。ワトスンと二人連れできたのは、一人旅の逃避行よりも目立ちやすいと考えたからだ。むろんそのほうが退屈しないで、旅が楽しいということもあったがね。それと、ここにたどりつくまでたっぷり十日間もかけたのは、きみに試行錯誤の時間を与えるためだ。むろん多少のかくれんぼも楽しんだよ。たとえば、きみが仕立てた臨時列車をぼくはカンタベリ−駅でやり過ごしたし、パリではきみはぼくたちが荷物を取りにくるだろうと見張っていたために二日間を無駄にしただろう? ぼくはちょっと試算してみたんだが、ロンドンからこのマイリンゲンにくるまでのル−トは主なものだけを拾い上げただけでも、少なくとも1024通りはある。ぼくはきみの頭脳なら、そのなかからぼくがもっとも採用しそうな確率の高いル−トを8通り以内に絞り込むことができるだろうと予想していたのだ。8通りといっても、それらを実際にチェックするのは、いまや手下がみんな逮捕されてしまったきみとしてはたいへんだったろう。 |
|
| いや、きみなら頭のなかだけで解を出すことができたかもしれない。(訳注12)いずれにしても、ぼくはきみが必ずぼくたちを見つけ出してくれると信じていたのだ。ぼくたちがゲミ峠を越えてダウベン湖にさしかかったところで岩石が崩れ落ちてきたときは、正直いってほっとしたよ。きみが追いついてきたことがわかったからね」 |
| ここまでしゃべったとき、モリア−ティ教授は、いきなり三度目の捨て身の攻撃をしかけてきた。今度ばかりはぼくも身をかわすだけでなく、彼の手首をつかまえて捩じりあげた。ナイフは地面に落ち、相手はぼくの腕を振りほどこうと必死にもがいたが、ぼくはそれを許さなかった。相手は上背があるので、まともに向かっていけば振り切られてもやむを得ないところだったが、ぼくが日本の格闘技バリツを多少心得ていたのが役に立った。ぼくは一旦背負い投げをかけて相手を崖っぷちの方へ投げ飛ばし、そこでこれまで実際に使ったことのなかった固め技のひとつを試してみた。それは相手の腕を徹底的に攻める技(訳注13)で、この技をかけられると、もがけばもがくほど腕が痛めつけられ、無理をすれば骨折や脱臼にいたる。ぼくにとっては、得意とするボクシングでやっつけるのがもっとも簡単だったのだが、ぼくはあえてその方法をとらなかった。 |
|
| なぜなら、ボクシングで殴り倒した場合、しばしば相手は脳震盪を起こして意識を失ったり、あるいはアッパーカットを食らって意識朦朧となり、正常な状態でなくなることがあるからだ。ぼくはそれを避けたかったのだ。モリア−ティには最後の最後まで正気でいてもらう必要があったのだ。自慢ではないが、当時ぼくは腕力にはかなり自信があった。ぼくはモリア−ティの腕を脱臼寸前まで捩じりあげたまま、真下に滝壺がみえる断崖の先端へにじりよった。しかしこれは、彼が突如として起死回生の反撃に出るやもしれず、ぼくにとっても冒険だった。彼は恐怖のため、身をこわばらせ、のどの奥から痰が詰まったようなひゅ−ひゅ−という妙な音を出した。 |
「さあ覚悟するんだ。これでぼくがきみを絶対に許さないと言った意味がわかったろう。無理やりスキ−服を着せられて、アイリ−ンがあのスキー場の崖の上で味わったのと同じ恐怖を、きみにもここでたっぷりと味わってもらおうじゃないか。あのスキー場の断崖よりも、ここのほうがスケールが大きくて、恐ろしさもきみにふさわしいぜ」
そう言ってぼくは、目もくらむような断崖の先端に彼の上半身を突き出した。水しぶきをあげて巨大な水の塊が切れ目なくはるか真下の滝壷へ轟音とともの落ちて行く光景は、身のすくむような恐ろしさだったが、ぼく自身もこの恐ろしさに耐えねばならなかった。この瞬間のためにこそ最後まで彼を正気にしておいたのだ。案の定、彼は恐怖にたまりかね、ぼくよりも上背のある体躯にものをいわせて突然暴れ出そうとしたが、その途端、逆手に締め上げていた彼の腕から、ぼきりと骨が折れる鈍い感触が伝わってきた。彼は悲鳴をあげ、よろよろと立ちあがると、だらりと下がった右腕を、苦痛のあまり思わず左手でかばおうとした。その一瞬のすきにぼくは彼を力いっぱい滝壺のほうへ突きとばした。滝の音でよく聞き取れなかったが、彼は何か叫ぶと、そのまま一直線に落下して行った。こうしてぼくはみずからの手でアイリーンの恨みを晴らしたのである。これが真実なのだ。 |
そのあとぼくがやったことといえば、前の晩手帳のペ−ジ三枚に書いておいた「親愛なるワトスン、ぼくはモリア−ティ教授の好意でこの短い手紙を書いている ── 」で始まるワトスンへの別れの手紙を、道に突き出た岩の上に置いて、風で飛ばぬようにぼくが日常使っていた銀のシガレット・ケ−スで押さえたこと、その手紙はモリア−ティ教授に対するぼくの一抹の憐憫の情として、教授とぼくの間で紳士的に決闘が行われた文脈にしておいたので、それに合わせて現場の足跡を細工したこと、ぼくも教授とともにライヘンバッハの滝壺に転落したと思わせるため、置き手紙のそばに、ぼくのアルペンストックをたてかけておいたことである。
ぼくは常々モリアーティ教授という男が、知能的にはぼくに勝るとも劣らない悪の天才であり「彼を抹殺することができたら、そのときは喜んで自分の生涯に終止符を打ってもよい」と繰り返しワトスンに語っていた。だから彼は少年から受け取った手紙がにせものだったことを知って大急ぎで滝へ引き返したとき、ぼくの予想したとおり、現場の状況からぼくがモリアーティとともに滝壷へ落下したと思い込んだ。 |
|
そして彼はこの事件を、まるでぼくが世のため人のため、悪党モリア−ティと闘って殉職したかのような美談に仕立て上げ「最後の事件」と題して公表したのである。しかし実態は、アイリ−ンを奪い去った男に対するぼくの復讐がすべてだったのだ。モリア−ティの死が社会の浄化に役立ったのは事実だが、ぼく個人にとってはそれは余祿でしかなかった。というよりも、その余禄の部分がぼくの犯罪──法によらず、みずからの手で罰すること禁じている世間的な意味での犯罪──の隠れ蓑になったのだ。完全犯罪の鉄則のひとつに「木は森のなかに隠せ」というのがあるが、復讐のためにモリア−ティを殺害したぼくの犯罪は、犯罪界の帝王に制裁を加え、害悪の根源を排除したことに対する社会的な賞賛という森のなかに隠されてしまったのだ。スイス警察が真実を解明する場合がなきにしもあらずと考え、それ以後の三年間ぼくは社会から身をひそめて様子を伺っていたが、結局ワトスンが公表した回想録「最後の事件」がそのまま事実の記録として世間に受け入れられるところとなった。そしてぼくは、社会へ復帰した後も、ワトスンに真実を打ち明ける勇気がないまま、ずるずると生涯にわたってずっと彼をだまし続けた。ぼくが心からワトスンの魂に許しを乞いたいのは、まさにこのことなのだ。
一方、アイリ−ンが死んでしまったので、彼女に対するぼくの本当の気持ちも、とうとうワトスンに明かすことはなく、ぼくは相変わらず女性に関して強がりを言い続けた。しかし、ぼくがアイリ−ンのことをいつも「あの女性」としか呼ばなかったので、彼女がぼくにとって、他の女性とはちがった特別の存在らしいということは、ワトスンもうすうす気がついてはいたようで、回想録「ボヘミアの醜聞」に書きとめられている。ただ、ぼくが彼女をどれほど深く真摯に愛していたかについてはやや認識に欠けるところがあるが。
そして ・・・・・ああ、また胸が痛み出した。長い間ぼくの話を聞いてくれて有り難う。いよいよ最後がきたようだ。何とか間に合ったよ。これでぼくも心おきなくあの世へ行ける。ううっ、やっぱり発作だ。でも、もう薬を飲むつもりはない。もういいんだ。有り難う。
さようなら。きみの幸運を祈る。
アイリーン、いまそっちへ行くよ・・・・・・
きみの
シャーロ |
|
|
(完)
|
訳注12 フォン・ノイマンとモルゲンシュタインはその著書「ゲ−ムの理論と経済学的
行動」(プリンストン大学出版局 1944年刊)において、「最後の事件」にお
けるホームズとモリアーティの各々の勝利の確率を数学的に分析している。そ
れによると、この場合ホームズが勝利を収める確率は40パーセントで、もし
大陸行きを中止した場合は60パーセントであったという。モリアーティが勝
つ確率はその逆であるが、注釈では、数学的勝算は間違いなく追跡者の側にあ
り、ヴィクトリア駅から列車が動き出した際、ホームズが死にさらされる確率
は48パーセントもあったと述べられている。
訳注13 「腕挫(ウデヒシギ)」という固め技のひとつである。
|
ストランドマガジン 合本6号1893年に掲載された「最後の事件」のイラストです。
ストランドマガジン 合本16号1898年に掲載されたイラストと下記のイラストを合成したものです。
ストランドマガジン 合本6号1893年に掲載された「最後の事件」のイラストです
管理人みっちょん
|
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|