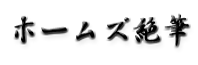|
(7) |
|
|
|
|
ぼくはブライオニ−荘を辞するとその足でスコットランド・ヤ−ド(ロンドン警視庁)のレストレイド警部を訪ねた。ぼくはたまたまワルシャワに知人がいなかったので、まだ犯罪に関わりあるとはいいきれない段階だったが、「ナダ−ル写真館」についての情報を ワルシャワ警察署経由で入手してほしいとスコットランド・ヤ−ドに無理やり頼み込んだ のだ。それから電報を一本打った。宛て先は、ぼくのちょっとした著作をフランス語に翻訳してくれたこともある友人で、当時パリで頭角を現してきた探偵のフランソワ・ル・ヴ ィラ−ルだった。「フランスの著名な写真家ナダ−ル」の線からワルシャワの「ナダ−ル写真館」の調査を依頼したのだ。そのあとは夕方まで別の事件の処理にいそがしかった。
夕方遅く、ぼくは一通の手紙を受け取った。手紙には日付がなく、差出人の署名も住所もなかった。封を開くと淡紅色を帯びた厚手の便箋に次のように書かれていた。
|
|
今夕八時十五分前、非常に重大な問題につきご相談いたしたく、ある人物が貴下をお訪ねいたします。最近貴下がヨ−ロッパの一王室に対して払われたご尽力は、どのような重要事件をも信頼してお任せできることを示しており、この点につきましては、各方面からも聞き及んでおります。前記時刻にはご在宅くださいますよう、また訪問者が覆面をしておりましても、お許しくださいますよう お願い申し上げます。
この手紙を調べているところへ、ひょっこりと現れたのはワトスンだった。彼に会うのは久しぶりだった。彼は自分自身の幸福な結婚生活にすっかり関心を奪われていたようだったし、ぼくはぼくで、すでに述べたように、相次ぐ海外の事件に没頭し、ベイカ−街の自分の部屋に席を温めるひまもなかったので、 二人の間は遠ざかっていたのだ。 ぼくはワトスンにひじ掛け椅子に掛けるよう手で合図し、葉巻のケ−スを投げ渡し、部屋の隅にある酒台やガソジンを指さして自由にやってくれと身振りで示した。しばらく見ない間に彼はかなりふとっていた。
|
「結婚生活はきみに合っているんだね、ワトスン。この前に会ったときからすると、七ポンド半はふとったね」
「七ポンドだ」
「そうか。もうちょっと考えて言えばよかったな。でも、もうちょっとあるんじゃないか ね、ワトスン。それに開業医に戻ったようだね。仕事に戻るつもりだという話は聞いてい なかったが」
「どうしてわかったのかな?」
「簡単なことだよ。だって、ヨ−ドホルムのにおいをぷんぷんさせ、右手の人指し指に硝酸銀の黒いしみをつけて、いつもここに聴診器を隠してるんですといわんばかりに片側がいびつに膨らんだシルクハットを持った紳士が部屋に入ってきたというのに、それが現役の医者だと見抜けないとしたら、ぼくはよっぽどのぼんやりじゃないか」
あまりに簡単なぼくの説明を聞いてワトスンは笑い出した。 |
|
「きみの説明を聞くと、いつもばかばかしいほど単純なものだから、自分でも簡単にできそうな気がするんだが、それでいてきみがそのプロセスを説明してくれるまでは、きみの推理のひとつひとつのつながりがまるでわからないのだからね。ぼくの目だって、きみと同じくらいにはいいはずなんだが」
「それはそうさ。きみは見てはいるんだが、観察していないんだよ。見ることと観察するのとは、まるっきり別物なんだよ」試みにぼくはワトスンに、彼が長年住んでいた二階のこの部屋へ上がってくる階段の段数をたずねてみたが、案の定、それが十七段あることを知らなかった。
そこでぼくは、彼が階段を見ているだけで観察していないからだと、ひとくさり観察について講釈をした。
(つづく)
|
イラスト スコットランド・ヤード写真提供 高田寛氏
ストランドマガジン合本2 1891年「ボヘミアの醜聞」のイラストです。
(管理人みっちょん) |
「ホームズ絶筆」に関する著作権を含む全権利は水野雅士に帰属します。
このページ掲載のテキストの無断転載、引用をご遠慮ねがいます |
|
|
|
|
 |
|