「ササッサ谷からライヘンバッハの滝までの小説」 参考資料
| Memories and Adventures by Arthur Conan Doyle (october 1923 to july 1924, The Strand Magazine) XXIII. SOME NOTABLE PEOPLE 1988年Greenhill Books版"Memories & Adventures" コナン・ドイル自伝『回想と冒険』第23章「著名な人々」より (2018年3月14日公開) |
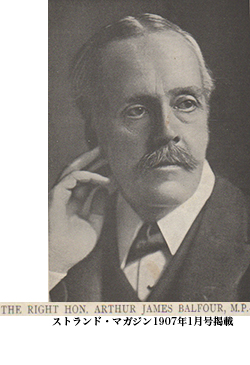 |
★「バルフォア卿」 熊谷彰訳と訳者解説 |
私とバルフォアの最初の出会いはなんともこっけいな経験だった。初代の老バーナム卿が私をビーコンズフィールドの田園屋敷に招いてくれた。すばらしい屋敷で、最初に建てたのは王党派詩人のウォラーであった。バークが近くに住んだことがあり、フランス革命宣伝の危険を示すため、あの芝居がかった瞬間に屋敷の床へ投げつけた短剣がいまだに陳列されていた。私はこの集まりをありありと覚えている。けれども、出席者の大多数は今では向こう側の世界にいる。ドロシー・ネヴィル夫人が両手に手袋をはめ、猫のように取りすましながら、ディズレーリの恋愛遊戯のうわさを言いふらしている。ヘンリー・ジェイムズ卿が頭を垂れ、木々の下を歩きながら、やがてインド総督レディング卿となる新進法廷弁護士に話しかけている。ローズベリー卿の母親であるクリーヴランド夫人が老いた顔に満面の笑みを浮かべて、ネヴィル夫人の話を聞いている。若きハリー・アーヴィングはバーナム卿のゴルフ談義にすっかり退屈したらしく、頭をかしげ、上等なベストのふくらみの向こうにあるボールを見ようとしている。これらの人々のかたわらにアスキス氏が微笑みながら立っている。こうして振り返ると、誰も彼もが影の世界内の影だったかのようである。
バーナム卿はトルコ式の風呂が趣味であり、屋敷の前面にすばらしい風呂を備えていた。屋敷に入ると右側最初のドアが乾燥室だったが、外見は簡素な居間であった。いつもの親切心でバーナム卿は私にトルコ式の風呂へ入るようにすすめた。それから大きなタオルで私をくるみ、頭に別のタオルを巻きつけて、乾燥室に落ち着かせた。ほどなく乾燥室のドアが開き、英国首相であるアーサー・バルフォアが入ってきた。屋敷の構造や流儀を全く知らなかったバルフォアが、驚きながら私を見つめたことを今でも思い出す。背後に続いていたバーナム卿が私を紹介したので、私は頭上のタオルを持ち上げた。説明は一言もなかった。だからバルフォアは、あれが私の通常の姿だと思いながらその場を去ったのではないだろうか。
私はその週末後、バルフォアには会わなかった。私の記憶では、そのとき彼は日曜の昼まで自室に閉じこもっていた。それから数年後に私は重大な家庭的喪失を経験し〔*最初の妻ルイーズの死/アンドルー・ライセットによる〕、ダンバー近くの小さな宿で自分を取り戻そうとつとめていた。私がその宿にいるのを聞くとバルフェアは親切なことに、わずか数マイルしか離れていないホィッティンガムから車を寄こして、ニ、三日こちらへ来ないかと誘ってくれた。ホィッティンガムには弟のジェラルド・バルフォアがいた。顔つきも態度も美しく洗練された人物で、アンドルー・ラングに似ていなくもなかった。ジェラルドの妻がリットン卿の娘である有名なベティ・バルフォア夫人である。縁故関係にあるこれらの家族──バルフォア家、セシル家、セジウィック家、リットン家の集まりを想うと、あたかもイギリス社会の一種の神経節のように見えてくる。この集まりの中にフランセス・バルフォア夫人もいた。彼女はアーガイル公の娘だが、私が覚えている限りでは父親に似ていなくもなかった。建築家兼古物収集家であるバルフォアの弟が彼女の夫であり、もうひとりの弟はロンドン・スコットランド連隊の大佐だった〔*これはドイルの誤解で、両者ともユースタス・バルフォアだと思われる〕。それから最後にアリス・バルフォア嬢がいた。たいへん気立てがよく穏やかで知的なこの女性が、私の実際の女主人であった。
アーサー・バルフェアは大いに意気が上がっていた。北ベリックでゴルフのメダルを勝ち取った所だったからだが、まるで学校生徒のように喜んでいた。どんな政治の成功もゴルフの勝利で得られるような強い喜びを兄にはもたらさないとアリス嬢が教えてくれた。ゴルフの腕前は人並みで、流儀は正統派、ハンディキャップは十から十二くらいであった。バルフェアは魅力的な招待主だった。良い聞き手で、相手が言うことを本当に聞きたがっているようだった。些細なきっかけで心から笑い、いつでも率直に話し、自分のことは控えめであった。私は長い間ひとりで暮らしていたので、ふだんよりも多弁だったことを覚えている。それでも彼は機嫌よく受けとめてくれた。
この大きくまとまりのない屋敷では、毎晩か少なくとも土曜夜に全使用人──総勢二十名ほどの女中や従僕が祈りのために集まった。それから屋敷の主人が祈りを読みあげた。使用人と大政治家がその日の罪の許しを求めて共に慎ましく祈り、我々すべての頭上にある存在を前にして、この世の区別が溶け去るのを聞くのは素晴らしかった。
ロシア艦隊が日本へ向かう途中で犯した不法行為を語ったときのバルフォアには大いに興味をそそられた。ドッガー・バンク漁礁で、この艦隊は英国トロール船への砲撃を始めたのである。あの穏やかな声を聞き、ものうげで私情を交えない態度に目を向けながら、こういう言葉を耳にするのは不思議な経験だった。「私はかんかんに怒っている。本当に、この事態にかんかんに怒っている。もし我々の艦隊が手近にいたら、奴らを海峡で止めようと考えただろう。むろん、圧倒的な力がなければできんことだ。流血を防ぎ、奴らの面子をつぶさないためにな。奴らの大使がその日の朝に来て、完全な保証をしてくれた。さもなくば、本当に何かをしなければならんかった。あの大使は自国の政府とひと悶着起こしたらしい。国の主張を曲げたと思われたのだ」
私はバルフォアに内閣がどのように動くかを尋ねた。それぞれの問題で決を取り、多数にしたがう。これは重要な事柄でなければだが、重要なときにはもちろん反対した閣僚は辞めなければならない、というのが答えであった。
私はバルフォアの性格の中に臆病さへの強い恐れがあるのに気がついた。他の何事もあれほどの軽蔑心は掻き立てないようだった。ジョージ・サックヴィル卿の話をしたときに、彼の顔面がすっかり紅潮したことを覚えている。それからサックヴィルは1759年のミンデンの戦いで解任されたし、射殺されてしかるべきだったが、それでもアメリカ戦役の際には陸軍大臣だった、と歴史を振り返った。さらに、これは私が口を挟んだのだが、サックヴィルはたいへんな放蕩者で、愛人の女優レイ嬢を真の恋人だったハックマン牧師が殺害した事件は18世紀の有名裁判のひとつだった。
あの訪問の思い出は私の記憶にいつまでも残るだろう。人生の暗い時期に差し込んだ一条の明るい光であった。あの古い屋敷がくっきり見えてくる。屋敷の外には折れた巨木があり、内部では国家の陰謀がその昔に企てられた。立派な書斎にはフランスの回想録が満ちあふれ、何よりもまず、この国の人々のためにあれほど働いたひとりの非凡な男がいる。そのころ私は心霊的な事柄の最重要さについて、後年そうなったほどの確信は抱いていなかった。だから、この訪問が当時でも間違いなく私自身のことより重要だった学識をさぐる機会であったかと思うと残念である。それから数年後、戦いが重く私にのしかかり、論争の舞台でほとんど孤立していたときに、私はバルフォアに手紙を出し、確信を分かちあっているのに守るのを私一人に任せているといって非難した。彼の答えはこうだった。「その問題に関する私の意見は確実にもう十分知られております」。私の説明の正しさを認めた返信だったのは確かだが、難局にいる私の支えにはそれほどならなかった。
★訳者解説:アーサー・バルフォア
米国大統領セオドア・ローズヴェルトに続いてドイルが回想したのは英国政治家アーサー・バルフォアである。
ドイルは1900年10月と1906年1月の英国下院議員選挙に2回続けて自由統一党から立候補した。残念ながらどちらも落選し、国政への挑戦は2回目の選挙で終わったが、ドイルが政治活動に最も熱心だったのはこの時期である。
このころ自由統一党は保守党と連立政権を組んでおり、バルフォアは1902年7月から1905年12月まで連立政権の首相をつとめていた。だから、ドイルが真っ先に取りあげてよい英国政治家である。
アーサー・バルフォアは1848年に生まれた。名門の出身で伯父ソールズベリ候に勧められて政界へ入り、この伯父の後を継いで首相になる。任期中に極東で日露戦争が勃発した。ロシア艦隊の「不法行為」にバルフォアが示した興味深い反応をドイルはこの部分に記している。
けれども、ドイルが主に回想したのはプライベートな出来事である。ユーモラスなエピソードがいくつか明かされているが、名門一族の交歓の様子も印象的に語られている。ドイルにとってバルフォア一家と親しくつきあった時期は「重大な家庭的喪失」がおきた時期でもあった。
アーサー・バルフォアは英国心霊研究協会〔SPR〕の会員だった。彼が心霊現象に興味を持ったのは若い頃からで、ケンブリッジ大学での恩師で姉エレナーの夫となったW・シジウィック、妹イヴリンと結婚したジョン・ストラット(のちのレスリー卿)たちと英国心霊研究協会の前身であるグループに創立当時から参加、1870年中頃にはバルフォア宅では有名な霊媒師を招いての交霊会が頻繁に開かれていた。英国心霊研究協会が1882年に創立されたときバルフォアは副会長で、シジウィックが会長であった。
その後、アーサー・バルフォアも英国心霊研究協会の会長になり、弟のジェラルド、姉のエレナー・シジウィック、妹イヴリンの夫レイリー卿も会長をしている。
しかし、心霊現象を科学的に立証出来なくても宗教として信じるようになったコナン・ドイルと根本的に違うのは、バルフォアたちが心霊現象をあくまでも科学的に立証する道を選んだことである。そして「真の科学と真の宗教は対立しない」と既存の宗教の信仰を続けている。ドイルは心霊主義の伝道活動に関連してバルフォアから受け取った返答を末尾に記しているが、これを読むと二人の歩んでいた道が違うことと、自伝執筆時のドイルの関心の有り様がよくわかる。
バルフォアは首相を辞めた後も政治活動を続け、1916年頃から1875年に亡くなった若き日の恋人メアリー・キャサリン・リットルトンが霊界からコンタクトを取っていることを信じるようになったが、信仰心は変わりなく1930年に亡くなった。
(心霊学関連の資料提供関矢悦子、参考文献は『英国心霊主義の抬頭』J・オッペンハイム著 和田芳久訳)
| 「コナン・ドイルの世界」に戻る |