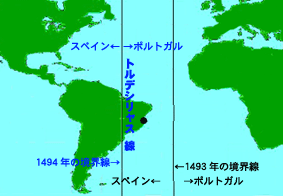|
||||||
| 「茶と砂糖」の歴史 (2) |
||||||
| み:「前回の表と重なりますが『茶と砂糖 の歴史 年表 2』の1637年の項目を見てください。オランダでの『茶』の流行についての記述です」 A:「『オランダの富裕な商人の家庭では主婦が客にサフラン入りのお茶を出すようになった。サフランを入れて飲んでいた茶は《緑茶》』ですね」 み:「この当時の茶会では砂糖やサフランを入れた『茶』を『カップからソーサー』にそそぎ日本の茶道を真似したような感じで『音をたててすする』のが教養ある人々のエチケット、とされていたそうですよ」 A:「う〜〜む。『茶』だけではなく『茶道』まで誤解されたとはいえ伝わっていたんですねえ・・・」 み:「この『お茶の会』があまりに流行って主婦たちが毎日のように『お茶の会』を開き家を留守にしたので多くの家庭が破滅しそうになったと、『紅茶の文化史 p27』に記されてました」 A:「お茶で家庭騒動ですか???」 み:「イギリスでも茶が流行りだすと『茶』への攻撃があるのですが、この時のオランダでも茶の排斥運動があり、茶をめぐる賛否両論の書物が出版される騒ぎになったようです」 A:「新しいものが流行ると非難するのは何時の時代にもあるんですね・・・ところでイギリスでも『茶』がオランダのように流行したのでしょうか?」 み:「それが『流行』した形跡はないようです。年表には『1630年代にオランダを通じてイギリスに茶が入る』と記してますが公式な文書に残っている『茶の輸入』は少し後のようです」 A:「『公式文書』前の資料はないのでしょうか」 A:「どういうことでしょうか?」 |
||||||
|
||||||
| A:「新大陸発見と言いますが、当時のアメリカ大陸には国も有りたくさんの人が住んでいましたよね。到達しただけでの『発見国』には何か利益があったのでしょうか」 み:「当時のヨーロッパでは『キリスト教支配者のものではない陸地を発見した主権国家は、ローマ教皇の許可さえ受ければ、新たに発見した土地の領有権を合法的に主張できる」と言うルールがありましたがさらに1455年教皇ニコラス五世はポルトガルに対し、ボジャドール岬以南のサラセン人(イスラム教徒)と戦い、これを奴隷とする許可を与えたのです。(大勅書ロマネス・ポンティフェクス)」 |
||||||
|
||||||
A:「種子島に『ポルトガル人』が来たのは偶然ではなくこの『トルデシリャス線』による『世界二分割』と言う理由があったんですね」 み:「そうですね。1500年にポルトガルがブラジルに到達して植民地として『砂糖」を栽培、その砂糖が世界一の生産高となり、1661年、キャサリン王女の輿入れの船のバラスト代わりに砂糖を詰め込めたのも『トルデシャリス線』によるスペインとの『世界二分割』が有ったからです」 A:「随分と長い説明だったけど何とか持参金として持ってきた『砂糖』の説明がついたようだから今度はこの後の説明をお願いしますよ」 み:「キャサリン王女が英国に輿入れをした頃から英国植民地での砂糖生産が多くなり、ブラジルの砂糖生産高世界一の座は譲り渡すことになりますが続きは次回と言うことでお待ちください」 |
||||||
| |
||||||